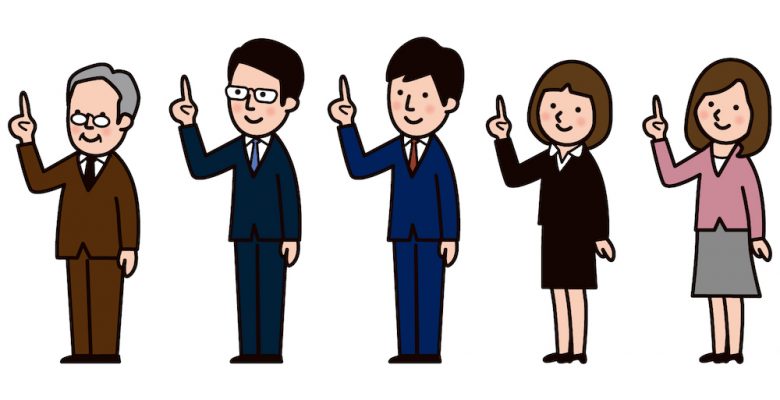畑恵氏が教える!教員の不足は大きな教育問題の一つ
子供が教育を受ける場所である学校は、安全で安心して通えることが求められます。
しかし、いじめ等の問題も起きており、それが深刻化してしまうことも珍しくありません。
教員同士によるいじめが発生したことも大きなニュースとなりました。
そんな学校で重要な役割を担うのが、子供に勉強を教えたり生活の面倒をみてくる教員の存在だと政治家の畑恵氏は言います。
子供達に直接関わることが多い分、その影響力も絶大です。
担任の先生によって、学校での生活が良くなったり悪くなったりすることもあります。
ただ授業で勉強を教えるというだけではなく、子供同士のトラブルがあった際などにも相談に乗ったり、間に入って話し合うなど人間形成の上で非常に重要な役割を担っています。
その教員の人材が不足しているということをご存知の方も多いのではないでしょうか。
全国各地にある公立の小学校や中学校で、教員が足りないという事態が発生しているのです。
その原因には色々あり、まず少子化を見越して正規雇用の教員の数を抑えて非正規雇用の教員の割合を増やそうという動きが考えられます。
臨時採用される教員は、出産や病気などで欠員が出た場合に補充されることが多くあります。
しかし、臨時採用の教員を確保するのは難しいのが現状です。
正規雇用と非正規雇用では待遇に大きな格差があり、正規雇用されないのであれば教員として働くことを希望しない場合も多くあります。
結果的に人材が不足して、臨時採用の先生を確保できない事態に陥っています。
学校では女性の教員も多く、出産で休むことも考えられます。
その現状に見合った教員の採用枠が用意されていないのが大きな問題です。
また、 教員を目指す若者が減り続けているのも大きな問題 とされています。
教員は長時間労働が当たり前で、残業で遅く帰らなければいけないことも日常化しています。
教員の労働時間を調査した結果、数年前よりも労働時間が増えているというデータもあります。
学校現場は日々変化しており、英語が必修化されたり柔道が体育に取り入れられるなど新しく対応しなければいけないことが沢山あります。
いじめ問題などでもアンケートを実施したり、いじめ対策を行うことも求められます。
それにより研修等も増え、報告書を提出しなければいけないといった雑務にかかる時間も増えています。
そういった書類佐生正業務におわれ、肝心の子供達と触れ合う時間が減ってしまうのは本末転倒です。
給食などでもアレルギーを持っている子供が増えたことで、以前よりも注意を払わなければいけないことも増加しています。
中学校では部活動を教員が行うことが普通で、平日には遅くまで指導を行ったり休日にも練習をする等長時間労働につながりやすい環境です。
また、教員の給与体系は民間の企業とは異なり、独自の法律で定められています。
給与の月額4%がみなし残業代として予め支払われることになっているので、いくら残業しても残業代が支払われることはありません。
休日出勤しても同様です。
ただし、自治体などで個別に休日出勤した場合の手当てを定めているところもあります。
その結果、勤怠管理がおろそかになり、長時間労働が強いられています。
その他にも保護者のクレーム対応といった問題もあります。
些細なことでクレームを言ってくる保護者もおり、その対応に頭を悩ませるケースも多いようです。
理不尽な要求をされたり、学校外のことまで頼まれたりすることもあります。
最近は日本に海外から訪れる人が増えた事もあり、外国をルーツとする子供が学校に通うケースも増えています。
日本語が上手く伝わらないこともあるなど、教員にかかる負担も大きくなります。
保護者の対応に時間をとられ、心身共に疲弊してしまう場合もあります。
それにより精神的な不調が生じる人もいます。
近年はワークライフバランスの考え方が浸透してきたこともあり、就職時に長時間労働を強いる環境を避ける傾向にあります。
残業が多く、休暇も取りにくい職場は、多くの人にとって魅力的とは言えません。
子供を持っても我が子と接する機会が減ってしまうなど弊害が大きいからです。
それに加えて、プライベートを充実させることで、仕事にもポジティブにリフレッシュした状態で取り組めるということもあります。
毎日疲弊しきっていたのでは、よい教育を行うことができなくなってしまいます。
教員の人材不足は、大きな教育問題の1つといえるでしょう。
子供の教育に携わりたいという大きな志を持った教員を育てるためにも、働く環境を整えることが重要になります。
勤怠管理をきちんと行って、それに見合った報酬を受け取れるようにすることも必要になってくるでしょう。
正規雇用の人数を増やしたり、正規雇用と非正規雇用の待遇差を小さくするといった取り組みも必要不可欠です。
部活動を外部委託するといった取り組みも検討され始めています。
教員の人材不足がさらに進行すれば、教育そのものの質の低下も避けられません。
最終更新日 2025年7月28日 by koseyy